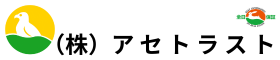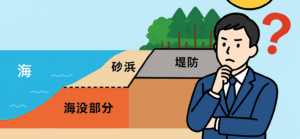不動産調査における「図面精度」の落とし穴
1.精度の低い図面で無理やり評価していませんか?
不動産の財産評価(相続税評価)や固定資産評価において、土地の形状や面積並びに最終的な計算結果を把握するために何らかの「図面」を用いることは欠かせない基本の部分です。
しかしながら、実務上の現場では次のような問題が生じていることが少なくありません。
・現在の「地図(14条地図)」ではない古い公図をそのまま根拠にしてしまう。
・地積測量図が存在しない場合、住宅地図や航空写真、自治体の地番図を採用してしまう。
・地積測量図が存在しても、古い図面の「残地求積」であるがそれをなんとなく採用してしまう。
・現況と図面が食い違っているのに「仕方ない」として進めてしまう。
こうした対応は、「手間を省き業務の効率化のため妥当である」と一見合理的な手続きに思えるかもしれませんが、最終的な計算結果(評価額)に大きな誤差を生じさせるリスクがあります。
2.なぜ精度の低い図面では問題なのか?
①公図や自治体の地番図は必ずしも正確ではない
→現在の「地図(14条地図)」ではない「古い公図(地図に準ずる図面)」や自治体が管理する「地番図(地番参考図)」は、基本的に土地の位置の概略を示すためのものであり、土地の形状や大きさ、縮尺の精度に欠けることがあります。特に古い公図は歪みが大きく、地積測量図と数メートル単位でズレることもザラにあります。
②登記簿の地積は現況を反映していないこともある
→登記簿に記載されている地積は、測量方法が旧来のものであることも多く、実測値と大きく異なる例も珍しくありません。特に調査対象地の地積が「残地求積」で求められている場合、残地求積が繰り返された最後の残地には大きな誤差が発生してしまいます。
③評価額に直結する
→土地の形状や面積が違えば、奥行補正率や間口狭小補正率、不整形地補正率などの適用数値も変わってきます。地積規模の大きな宅地の適用等には面積要件がありますので、その可否により数百万円単位で評価額が違ってくることもあります。
3.「精度の低い図面での評価」は誰のためか?
精度の低い図面をそのまま使うのは、評価する側にとっては確かに効率的で楽かもしれません。
しかし、納税者や依頼者にとっては大きな損失につながる可能性もあるのです。
- 本来より高い評価額となり、相続税や贈与税等を過大に負担することとなる
- 逆に低い評価額となり、税務調査等で否認されるリスクを背負う
どちらにしても納税者や依頼者にとっては不利益になる場合があります。
4.これからの評価のあり方
財産評価や固定資産評価においては、評価担当者は「使える図面」ではなく「使うべき図面」を慎重に選ぶ姿勢若しくは「図面を作成」する姿勢が求められます。
- 精度の高い地積測量図や14条地図、現況測量図面があれば最優先で採用する
- 公図や地番図等しかない場合でも、必ず現地確認や航空写真との照合を行い実測と突き合わせ精査する
- 過大な誤差が生じる場合には誤差の可能性を依頼者等に説明し、必要に応じて現況測量等を依頼する
評価業務の本質はいかに「客観性」と「妥当性」を確保するかです。
精度の低い図面を安易に採用することは、その後の信頼性を損ねる行為にほかなりません。
5.終わりに
「図面の精度に左右される評価」をどう扱うかは、実務者の姿勢次第です。
評価の精度を軽視すれば、依頼者等に損害を与え、ひいては自社や自らの信用を失うことになりかねません。
精度の低い図面で無理やり評価していませんか?
――いま一度、評価の手続き及びその方法を見直す必要があるのではないでしょうか。
6.<豆知識>
”第3 争点に対する判断…しかしながら、被告の地図情報システムに取り込まれた本件画地の地番図データによれば、地積が1893.721平方メートルしかなく(β3の2)、本件地積測量図によって計測され、登記もされている1839.27平方メートル(113番13土地の地積)と209.64平方メートル(113番14土地の地積)の合計2048.91平方メートルより155.189平方メートルも小さく、割合は92.4%にとどまっていて、誤差の範囲を優に超えており、正確性に疑問がある。”
令和 4 年(行ウ)6 固定資産価格審査決定取消請求事件
宮崎地方裁判所 令和 6 年 11 月 13 日 判決
仮に対象地の登記上の地積が100㎡で、旧公図や地番図をCADソフト等で計測した結果が90㎡の場合、約10%前後のズレが生じますが、地方裁判所の判断によれば上記のとおり約8%前後でも「誤差の範囲を優に超えており、正確性に疑問がある」と示されています。
筆者の所感では、不動産登記規則第10条4や国土調査法施行令別表第四を勘案し「市街地地域・村落地域・農地地域」では「3~5%以内」(欲を言えば「市街地域:3%以内」「村落・農地地域で5%以内」)、「山林・原野地域」で「5~10%以内」が上記判例をも踏まえた図面採用時の妥当な許容範囲であると考えています。
※上記事例は、自治体(被告)と土地所有者(原告)が採用した「図面」について争った事例であり、最終的に原告側の主張が認められ固定資産評価額約-240万円が認容された事例です。