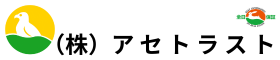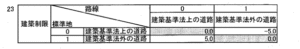【判例紹介】写真一枚千円?物件写真の著作物性を認めた裁判例
普段の分野と少し離れて、今日は不動産仲介分野の判例を一つご紹介します。
不動産仲介の現場では、物件写真(外観、内観、周辺環境等)を撮影して自社HPやスーモ等の不動産ポータルサイト、その他の広告等に掲載することが当たり前のように行われています。
学生の頃、賃貸需要旺盛なエリアで某不動産賃貸仲介会社のアルバイトをしていたのですが、原付バイクで物件写真を撮りまくり周ってました。
そのような写真を「他社が無断で利用」した場合、一体どうなるのでしょうか?
結論から言ってしまえば、今回ご紹介する判例(東京地裁 令和6年2月7日)では、
「一眼レフカメラではなく、スマホで撮影した物件写真にも著作権が成立する」と認定され、損害賠償が命じられました。
1.事案の概要
- 原告:不動産仲介会社(Y)
- 被告:不動産仲介会社(X)とその代表(代表は原告の会社の元従業員)
- 争点:不動産の物件写真108枚の無断使用の損害賠償
- 原告の請求:写真1枚当たり2万円×108枚=216万円(+法定利息の遅延損害金)
- 被告の反論:「撮影者の独自性はなく著作物性はない」「スマホなどを使用して素人が撮影したものにすぎず・・・撮影代行サービスを利用しても1枚当たり100円前後で入手できる」等
2.裁判での争点と判断
①物件撮影写真に「著作物性」があるのか?
被告は「被写体の選択、構図の設定等表現上の要素は非常に限られたものとなり、撮影者の独自性は表れない。」と、著作権法上保護される著作物に当たらないと主張しました。
しかし裁判所は、以下の点から著作物性を認定しました。
- 賃貸物件の内容を分かりやすく需要者に伝えるため、明るさや撮影角度等を調整して行われたもの・・・対象を広く写真に収めるため、パノラマ写真を撮影できるカメラを利用して撮影されたものも含まれている
- 写真は、被写体の構図、カメラアングル、照明、撮影方法等を工夫して撮影されたものであり、撮影者の個性が表現されたもの
<結論>:写真は、思想又は感情を創作的に表現したものと認められ、「著作物(著作権法2条1項1号)」に該当する
②著作権は誰のものか?
- 撮影者は原告会社の従業員
- 物件情報サイトへの掲載を目的に、業務として撮影
<結論>:職務著作(著作権法15条)として、原告に帰属
※ただし71枚についてのみ認定され、それ以外は写真の撮影日や原告会社従業員の入社日等の関係から不明とされました。
③侵害行為の有無
- 被告会社は、対象写真を自社サイトで公開していた
- これは著作権(複製権・公衆送信権)の侵害にあたる
④権利濫用にあたらないか?
- 被告側は「原告代表がネット上で誹謗中傷をしていた」として著作権侵害に基づく損害賠償請求は、権利の濫用であると主張しました。
- しかし裁判所は、被告会社に対する不法行為が成立し得るか否かは別として、著作権侵害に対する請求自体は正当(直ちに権利の濫用にはならない)とし、この主張を退けました。
⑤損害額の算定
ここが実務上の注目点です。
- 原告主張:1枚2万円(NHKエンタープライズや毎日フォトバンク、アマナイメージズ等の基準を引用)
- 裁判所判断:裁判所は、市場の撮影代行サービスの料金を参考にしました。
不動産写真の撮影は、外観・内観セットで3,000円~5,000円程度
パノラマ撮影で3,000円台
30枚撮影しても1万円前後といった水準で提供
1枚あたり数百円程度が相場だと認められました。
これに加え、
- 今回の掲載期間は2か月弱
- 著作権侵害に基づく損害額は、通常の使用料よりもやや高めに算定されるべき
<結論>:上記の事情を考慮し71枚 × 1,000円 = 7万1,000円が損害額と認定されました。
3.判決の結論
- 被告らは連帯して原告に 7万1,000円+遅延損害金 を支払え
- それ以外の請求は棄却
- 訴訟費用は大部分を原告負担(24/25)
つまり、原告が請求した216万円のうち、認められたのは約3%程度に過ぎませんでした。
4.実務への示唆
この判例から学べることは大きく3つです。
- スマホで撮った不動産写真でも著作物になる
→ 「どうせ定型的な写真だから大丈夫」とは言えない - 損害額は市場価格ベースに基づいて算定される
→ 高額請求しても、実際には相場ベースで認定される傾向 - 写真利用は必ず権利関係を確認すること
→ 自社撮影か、使用許諾を得ているか、社内でチェックする体制が重要
5.まとめ
この事件は、「たかが物件写真」と軽視されがちな著作権問題に警鐘を鳴らした事例です(住宅地図等の複製配布等も著作権問題になります)。
一方で、損害額は現実的な相場で算定されることも示されました。
(数枚パクられた程度では訴えの利益があまりないので、転載できるものは転載してしまえという悪質業者を増やしてしまうような判断基準を示してしまったような気もしますが…)
不動産業界では、写真素材を取り扱う業務が日常的に行われます。
「転載してもバレないだろう」という軽い気持ちが、訴訟リスクにつながりかねません。
写真は小さな1枚でも「著作権あり」。利用は慎重に、が鉄則です。
コラム:不動産広告は「広角写真」から「動画」へ
今回の裁判は物件写真の著作権をめぐるものでしたが、不動産広告の現場では少しずつ潮流が変わってきています。
かつては「広角レンズで部屋を広く見せる写真」が集客の王道でした。しかし最近では、
- スタッフが物件内を歩きながら解説する動画
- 360度パノラマ写真やVR内見
- TikTokやInstagram向けのショート動画
など、体験型で住んだときのイメージが湧きやすいコンテンツ”が主流になりつつある気がします。
消費者も「実際に住んだらどうか」というリアルな情報を求める傾向が強まり、
単に広く見せる写真よりも、安心感や透明性のある情報提供が支持されていると思います。
また、動画であれば他社が転載しづらいとも思います。
写真の著作権トラブルは依然リスクとして残りますが、
今後の不動産マーケティングは「写真から動画へ」の変化を前提に考えていく必要があるでしょう。