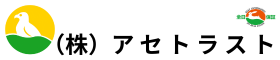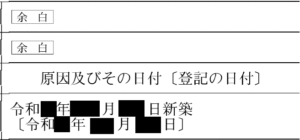【行政問題】固定資産評価は制度自体が不完全
私たち市民が毎年支払っている固定資産税(都市計画税)(※取得時は、不動産取得税や登録免許税も)。
その基礎となる土地や建物の「評価額」は、どのように決められているのか知らない人が大半です。
日本の大都市を含め、多くの地域では国土調査が行われておらず、正確な地図や図面が存在しないのが現状です。
地籍調査の進捗状況はいまだにおよそ50%弱です。都市部ほど整備が進んでいません。
上記の土地の登記の基礎となる図面の多くは、明治時代につくられた不正確なものです。
間口、奥行、形状、地積といった評価の前提となる情報に、誤りが含まれている可能性は決して否定できません。
さらに制度上の問題として、固定資産評価は毎年1月1日の「現況」に基づいて評価することになっています。しかし、全国に約1億8千万筆ちかくもある土地の現況を毎年チェックすることは、物理的に不可能です。そのため、現況主義は“努力規定”にとどまり、実際には何十年も放置されて現況と登記が食い違ったままになっている土地も珍しくありません。
税務課の職員は2〜3年で異動することが多く、評価替えを経験しないまま他部署に移ってしまうケースもあります。結果として、評価の点検に時間も割けず、スキルも蓄積されにくいのが実情です。また、少子高齢化に伴う職員の減少や財政的余裕の減少も重なって、「ヒト、モノ、カネ」のすべてにおいて限界がきているのではないかと感じています。
評価制度の欠陥は複雑な基準の随所(地区区分の設定、標準宅地の鑑定、路線価の敷設、画地認定、評価手法等)に内在していますが、多くの納税者は「評価額そのもの」よりも「税額の増減」にしか関心を持たないため、問題が表面化することは滅多にありません。仮にニュースになっても、「職員の理解不足・怠慢」といった個人の資質に原因を求めがちで、制度そのものの構造的な欠陥にはあまり目が向けられておらず議論も進んでいないのが現状だと思います(確かに怠慢などのも一部はあるかもしれませんが、前任者からの引継ぎや専門知識の教育が十分でなく、そうならざるを得なかった気の毒な担当者の方も相当数おられると思います)。
一方で、市町村側も「誰からも苦情が来ない」ことを理由に、「評価に問題はない」と判断してしまう状況があるのではないかと思います。
では、私たち納税者にできることは何でしょうか。
まず一度、自分の土地や建物がどのようなプロセス(計算過程)で評価されているのか、税務課に確認してみることをおすすめします。
もし専門的で分かりにくいと感じるのであれば、専門家に同行してもらうもしくは代理で聞いてもらうのも良い方法です。
住民が固定資産評価制度の仕組みに関心を持つことは、単なる税額の問題にとどまらず、行政内部に知識や経験を蓄積させる大切な契機になります。市民の目が意識されれば、人事異動のあり方や評価制度の改善、情報開示の徹底、説明責任の遵守・透明化等にもつながるかもしれません。
地方自治とは本来、地域住民の自らの意思と責任に基づき、地域の実情に応じた行政活動を行うことです。
固定資産評価制度の幾多の課題を考えることは、単に税金の話ではなく、地方政治の住民参加のあり方を見直すきっかけになるかと思います。
納税者の無知によって、制度を支えるのが私たちの本意でしょうか?
“税金は黙って嫌々払うもの”ではなく、“納得したうえで負担するもの”であるべきではないでしょうか。
私たち一人ひとりの関心と行動が、「より公正で信頼できる行政」「ずっと住み続けたい街」につながっていくのではないでしょうか。