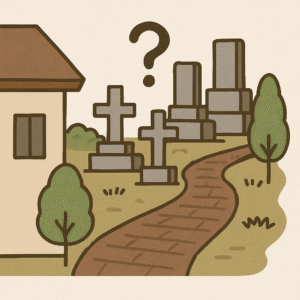【固定資産税】毎年支払っているその固定資産税、本当に「適正」ですか?
固定資産税の課題徴収の実態
固定資産税(都市計画税含む)は、不動産を保有するにあたり、切り離して考えることのできない税金ですが、「固定資産税」の「過大徴収」「誤り」「過誤」という言葉が、未だ世間一般に知られているものではないように思います。
Gemini(GoogleAIアシスタント)より
※音声中「たつらん制度」→「縦覧制度」です
固定資産税
毎年1月1日に、『土地』『家屋』『償却資産』を所有している者がその固定資産の「価格」を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村(東京都特別区の場合は東京都)に収める税金
通常は、行政(自治体)が算定する税額が間違っているはずがないと考え、言われるがまま支払っていることが多いと思いますが、その計算は市区町村の課税担当職員が基本的に行っています。ただ、この地方公務員は3年ほどで部署異動を行う「ジョブローテーション」制度が一般的であり、そのような短期のローテーションでは技術や経験の蓄積ができづらいことは一般企業にお勤めの方であればご理解できるかと思います。
事実、行政側の課税誤りにより過大徴収される事案が幾度となく発生し、地元の新聞報道若しくは全国紙などのニュースで報じられることもありますが皆様はご存知でしょうか?
| 時期 (リンク有) | 都道府県 | 市区町村 | 概要 |
|---|---|---|---|
| R7.7 | 東京都 | 文京区 | 土地・家屋の旧所有者に対して、誤って固定資産税などを課税していた 所有者が変更されていたのに、以前の所有者74人に固定資産税などを課税しており、このうち21人はすでに納付を済ませてしまっていた 東京法務局が登記情報の変更を都に伝えていなかったことが原因 旧所有者からの問い合わせを受けた都が調べたところ、24年中に所有権を変更した74人に固定資産税と都市計画税を誤って課税していたことが判明 |
| R7.6 | 山口県 | 長門市 | 固定資産税の軽減措置の対象となっている老人福祉施設などが建設された3か所の土地について、誤って多く課税。 県内の他の市でこの措置が適用されていないことがわかり、ことし4月の県からの通知を受けて確認したところ、市内の有料老人ホームやグループホームが建設された3か所の土地について固定資産税の負担が軽減されていなかった。 軽減されていなかった期間は2007年度から昨年度までの18年間で、金額は882万余り |
| R7.6 | 新潟県 | 村上市 | 旧神林村が市道用地として1989年10月から98年3月の間に住民から取得した土地について、誤って固定資産税を課税していた 対象は8人で、さかのぼれる2016年度からの約1万8千円について返還や修正 |
| R7.5 | 青森県 | 今別町 | 住宅用地への固定資産税を減額する特例措置の適用ミスにより、町民2人から計168万2300円を過大に徴収していた |
| R7.5 | 福島県 | 須賀川市 | 事務処理のミスにより、総額200万円あまりの課税誤り 年間で、固定資産税・都市計画税について、個人と事業者34件、あわせて約200万円を、誤って税率を多く算出 |
| R7.3 | 福岡県 | 遠賀町 | 法人が所有する家屋1棟に対する固定資産税について、29年間にわたって過大に課税する誤り 20年分の過大課税分と加算金計約6200万円を法人に返還 1995年に家屋を固定資産課税台帳に登録した際、構造を誤った。町要綱で返還は20年分までと定められていた |
| R7.3 | 沖縄県 | うるま市 | 2022~24年度の固定資産税を計約1900万円過徴収 土地や家屋に関する法務局のデータを手作業で入力していたことなどに伴うミス、住宅特例が適用される施設の見落とし、課税地目の誤り 22年度は46件約550万3600円、23年度は37件285万2300円、24年度は65件1079万1700円を過徴収 「他の税は申告に基づくが、固定資産税はこちらで建物や土地を評価するので、その中で間違いが生まれてしまった」 最も過徴収額が大きかったのは24年度分の老人施設で、市は金額を明らかにしていない |
| R7.1 | 和歌山県 | 広川町 | 固定資産税の計算を誤り、平成17年度以降の20年間に、およそ1億4500万円を過大に徴収 資材置き場や駐車場などに利用されている土地で、課税額のもとになる「課税標準額」を誤って高めに算定 土地所有者からの指摘で問題が発覚し、町は、職員の認識不足などが原因 |
| R7.3 | 群馬県 | みなかみ町 | 町内の法人に対し建物の固定資産税を過大に請求 20年間に過大に徴収した2564万2200円に利息相当額を加えた計3418万3900円を返還 法人側から「家屋の評価におかしい点がある」と問い合わせがあった。 町が調査したところ、建物の評価額を算出する際に、誤った基準で計算 |
| R7.4 | 兵庫県 | 尼崎市 | 神戸地裁尼崎支部は22日付の判決で原告の主張を全面的に認め、請求通り約1億9300万円の支払いを市に命じた。市は判決を不服として大阪高裁に控訴する方針 訴訟は線材加工メーカー「日亜鋼業」が提起。市によると、同社は同市道意町に所有する土地を税制上の「大工場地区」ではなく、「中小工場地区」として市が評価していたことに注意義務違反があると主張。対象の土地は大工場地区とみなされると納税額が一定程度減る。 市は18~21年度分の過大徴収分の金額を返還。同社は17年度以前の納税分でも返還を求めたが、市が応じなかったため22年10月に提訴していた。 |
| R7.1 | 広島県 | 廿日市市 | 木材港北と木材港南の両地区の17法人について、固定資産税と都市計画税を多く徴収する課税ミスがあり、約4500万円を還付 |
| R6.10 | 神奈川県 | 南足柄市 | 非課税の建物に26年間、誤って市税(固定資産税・都市計画税)を課し続けていたとして、建物を所有する法人に5600万円を返還すると発表 建物は公益性の高い法人が所有する事務所や倉庫で、非課税だった 法人側税理士の指摘で課税ミスが判明 |
| R6.9 | 秋田県 | 湯沢市 | 民間事業者と市が共同で所有している施設について、誤ってすべてを民間事業者の所有として、9年間、固定資産税を徴収していた 誤徴収した金額は、2300万円以上 誤徴収があった施設は、2015年に建築され、民間事業者と市がそれぞれ区分所有しています。しかし、湯沢市は、すべてを民間事業者の所有として、9年間、固定資産税を徴収 市は、利息相当分と合わせて2730万円あまりを民間事業者に返還 施設の利活用について市役所内で協議していた際にミスに気付いたもので、施設が完成した際に、当時の市の担当職員が施設の所有者を“民間事業者のみ”と課税台帳に記載したことが原因 |
| R6.6 | 栃木県 | 那須町 | 75人に対し、本年度の固定資産税を過大に課税する誤りがあった 過大徴収していた額は計23万1900円 土砂災害特別警戒区域に指定されている土地は評価を減額する補正が適用されるが、一部で補正が適用されていなかった |
| R6.4 | 千葉県 | 長柄町 | 工場や事務所などの固定資産税評価額の算出を誤り、本来より高く課税していた。 地方税法と町要綱に基づき、約3千万円を還付・返還 |
| R6.4 | 兵庫県 | 芦屋市 | 地評価額の算定プログラムに設定ミスがあり、900人に計66万3千円を過大請求、73人に計5万9500円を過小請求 土砂災害警戒区域などで土地評価の補正率が誤っていた。市が算定プログラムの更新を発注した際、業者が設定の変更を誤った |
| R6.3 | 千葉県 | 四街道市 | 固定資産税を過大徴収 四街道市、最大5713万返還 |
| R6.3 | 宮城県 | 栗原市 | 市内の工場と事務所各1棟の固定資産税を過大に徴収していた 両物件の所有会社に還付加算金を含め計1332万4700円を返還 市によると、2棟とも1979年築の鉄骨造だが、固定資産税を評価する際の構造を「鉄骨・鉄筋コンクリート造」と誤って算定 |
| R6.2 | 埼玉県 | 熊谷市 | 市内のビル1棟で1972~2022年度の51年間にわたり、固定資産税と都市計画税を過大徴収 税額の根拠となる不動産の評価額を、県が誤って過大に算出 市はビルを所有する企業に対し、14~22年度の9年分については過大徴収分約8350万円と利子相当分の計約1億円を返還する方針 法律上の時効は5年だが、市の要綱に沿って10年さかのぼり返還などをする。1972~2013年度分は返還しない ビルは鉄筋コンクリート製で1971年に完成。当時、熊谷県税事務所が単独で不動産評価を担当したが、担当者が誤った数値を使うなどし、本来よりも過大な評価額になっていた |
| R4.11 | 福岡県 | 久留米市 | 固定資産税の評価を誤り、平成15年度から計約6700万円を過大に徴収していた 利息に当たる加算金を含めて88筆の計約9200万円を返還 職員が固定資産システムに入力する際、農業用施設用地として評価すべきところを、誤って宅地として入力していた 市民から「土地の税金が高い」と問い合わせがあり発覚した。市は「職員の知識が不足しており、研修やチェック体制の強化に取り組む」としている 課税ミスは12~14年度分でも確認されたが、市の規定に基づく返還期間の対象外 |
| R4.11 | 広島県 | 廿日市市 | 廿日市市で5000万円を超える固定資産税を誤って多く徴収 有料老人ホームの住宅用地について、固定資産税の特例適用の状況を確認していたところ、1施設で適用漏れ その後、調査したところ、合わせて4施設で同様の特例適用漏れ 土地を所有する法人や個人など、合わせて10件に対しおよそ5200万円を返金する予定 |
| R4.10 | 静岡県 | 牧之原市 | 市民1人から28年間にわたり宅地の固定資産税を誤徴収していた 市要綱に基づき、20年分の固定資産税など170万円を男性に返還 市民は1996年に山林と畑の土地を購入。市が所有権移転に伴う課税情報を変更した際、誤って宅地も移転の対象として処理した |
| R4.6 | 香川県 | 三木町 | 固定資産税の課税を誤っていたのは、2017年度新築の家屋130棟、納税義務者120人 評価替えの際、2017年度新築の家屋について「経年減点補正(建築から経過した年数に応じて減価する)」が適用されておらず、2021~2023年度の評価額及び課税標準額が2018年度の評価替えのまま据え置かれていた 130棟の家屋の納税義務者120人に対し、本来835万円あまりの課税総額となるところ、668万円あまり多く課税していた システム業者がプログラムの更新を怠っていたことが原因 |
| R4.5 | 埼玉県 | 川越市 | 土地の評価方法の誤りが原因で固定資産税と都市計画税の課税ミスがあり、169万円あまりを返還 評価する土地に接していない路線の路線価を基に税額を算出し、徴収していた 計18人から過徴収していたことが判明 市の返還金取扱要綱に基づき、02~21年度分の返還を決めた 対象者は16人で、返還金額は利息などを含めて計169万3300円 96~01年度に計1万千円を過徴収した残る2人については、法律などに根拠となる規定がないため返還せず、本人に課税ミスがあったことを通知して理解を求める予定 |
| R3.12 | 沖縄県 | 北谷町 | 10年間、町宮城の大規模マンション各戸の固定資産税を、本来の評価額より高く算定し、総額約1314万円を過大に徴収 対象者は634人、マンションは19階建てで421戸ある。返還される平均額は各戸当たり約3万3千円 町内であまり例のない大規模マンションだったため、図面や工事見積書などを基に算出する計算法を用いたため評価額を誤った 所有者側から「固定資産の評価額が高いのではないか」と審査申し出があり誤りが判明 |
| R3.9 | 沖縄県 | 沖縄市 | 1970年から2014年に建築された一部の複合構造家屋について、固定資産税の算出に誤りがあった 過大課税による還付対象者136人(151棟)に4020万円を還付、過少課税による追徴対象者12人(15棟)から254万円を徴収 追徴課税は法律に基づく時効とならない過去5年分を対象とする。還付については市独自の判断として過去20年分まで還付 鉄筋コンクリート造や鉄骨造など複数の構造でできた家屋の固定資産税評価について、面積の大きい部分の経年減点補正率を適用すべきだったが、面積が小さい部分を適用してシステム入力してきたことが原因 |
| R3.2 | 島根県 | 安来市 | グループホームや有料老人ホーム6カ所の土地に対し、住宅用地の特例措置を適用していなかった 施設も人が常時居住するため、本来は住宅用地の特例措置の適用対象 固定資産税を過大徴収していた期間は最長で30年間にわたるというが、市の要綱では返還は過去20年分と定めており、加算金を加えた返還額は2300万円余り |
| R3.1 | 福島県 | 国見町 | 町内3つの会社から最長で1993年から誤徴収、約1300万円を返還 |
| R2.10 | 京都府 | 木津川市/京田辺市 | 中小企業団体などが所有・使用する建物に誤って課税していた 木津川市では3棟に対して最長44年間、京田辺市では1棟に対して41年間、誤って課税していた 両市とも要綱に基づき、20年間分の固定資産税と加算金を返還し、木津川市では返還額は計998万円、京田辺市では730万円 地方税法では学校法人の学校や宗教法人の寺社、社会福祉法人の老人福祉施設などの固定資産は非課税となっているほか、農業協同組合や健康保険組合、労働組合、中小企業団体などが所有・使用する建物も非課税 |
| R2.9 | 大阪府 | 泉大津市 | 家屋が新築された14件の土地について、小規模住宅用地の特例措置の適用を漏らしていた 課税の誤りは1999~2020年度の22年間にわたるが、市の要綱で対象となる20年間分の固定資産税1047万円分を返還し、利息に相当する加算金を加えた返還額は計1380万円 入力を漏らした理由は分かっていない。今年度の評価替えに合わせて新たなシステムを導入し、データを検証する過程で誤りが見つかった |
| R2.8 | 滋賀県 | 湖南市 | 会社の社員寮として使われている土地1200平方メートルに対し、住宅用地の特例措置を適用していなかった 誤っていたのは79~20年度の42年間にわたるが、市の要綱では返還期間は過去10年分。20年度分は途中で課税の誤りを修正したため、19年度までの9年分の過大徴収額320万円と加算金30万円を返還 |
| R2.6 | 東京都 | 狛江市 | 18~20年度の固定資産税で家屋の評価額を誤り、納税者約990人に対して固定資産税約1400万円を過大に徴収 狛江市では18年度の評価替えを前にシステムを入れ替えた際、14~15年度に新築された家屋の一部について、当時の再建築費評点補正率(木造1・05倍、非木造1・06倍)を2乗して評価額を算出したため、家屋の評価額が過大となっていた |
| R2.4 | 沖縄県 | 国頭村 | 2009~18年度にわたり固定資産税を誤徴収していた 固定資産税の誤徴収を巡っては昨年3月、村民からの問い合わせで、村が09~18年度に固定資産税を680件(約893万円分)過小に、40件(約336万円)を過大に徴収 家屋の評価額を計算するシステム操作の人為的ミス |
| R2.2 | 大阪府 | 大阪市 | 市独自の評価ルールに基づき徴収していた家屋の固定資産税について、過大請求していた 国家賠償請求訴訟で市の評価ルールが違法と判断されたためで、対象となる建物の所有者は約3万人で、還付額が約16億円に上ると推計 還付対象は昭和53年~平成16年に新築され、市独自の評価ルールを適用した約6千件の建物。市では地盤の特性から建物の基礎工事で通常より太く長いくいを使用しており、市長の裁量で国の固定資産評価基準でない市独自の計算方法を用いていた 平成26年に市内のマンション所有者が市の評価ルールは違法として、大阪地裁に国賠訴訟を提起。地裁は市の違法性を認め、2審大阪高裁もこれを支持。最高裁が昨年12月17日付で市側の上告を棄却し、1、2審判決が確定 |
| R1.9 | 沖縄県 | 南風原町 | 土地の固定資産税を約1400万円過剰に請求していた。過剰徴収額に利子などを加えた約1900万円を計上 還付の対象となるのは、7月31日時点で過剰請求が判明している43筆(35件)、50人 要綱に沿って43筆(35件)中、29筆(24件)には最長20年までさかのぼって返還金が支払われる 通常であれば住宅建設中に「非住宅用地」として課税し、完成後に「住宅用地」として認定し直して「住宅用地特例制度」を適用しなければならないが、その一連の手続きをするための情報連携が担当者間でなされていなかった |
| H31.3 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 市内住宅用地の固定資産税について、284の個人・法人(376筆分)から過大に税を徴収していた 税負担を軽減する特例措置が適用されていなかったことが要因、住宅用地の広さに応じて課税額を減免する地方税法上の特例措置が適用されていなかった 還付金として約7600万円を計上 地方税法上、過去5年分の14年度までしか還付することができないが、過去20年分までさかのぼれる市の要綱に従い、台帳に記録が残る04年度分まで返還 |
| H30.11 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇空港、航空自衛隊、陸上自衛隊用地を3施設ごとに評価し固定資産税の過大徴収が生じた 約4500人への返還金が約9億円に上る 3用地を施設ごとに評価した06~08年度と負担調整や地価の上昇で差額が出た09年度から17年度までの11年間を返還の対象 市がこれまで一団の土地として評価していた3用地を06年度の評価替えで別々の土地として評価したため、陸自用地と空自用地の評価額がそれまでの評価額よりも高くなった。09年度には地主の意向で3施設を一団の土地とする評価方法に戻した 裁判所は3施設を別々に評価した市の判断を違法とした |
| H30.3 | 長野県 | 軽井沢町 | 平成27~29年度の3年間にわたり、軽井沢町が固定資産税を過分に徴収していた 平成26年11月に積雪・寒冷地域の固定資産税の評価基準が改正されたが、適用されていなかったことが原因 対象となるのは家の構造が、軽量鉄骨造、レンガ造、コンクリートブロック造の非木造家屋 3年間で1758棟に上る。還付金額は合計2,520,800円 |
| H29.5 | 徳島県 | 徳島市 | 市が一部の課税者を対象に行った調査では、計228件2億532万円を多く徴収していた 16年度が38件4026万円、15年度40件3604万円、14年度32件3153万円、13年度72件4962万円、12年度は46件4787万円 半数以上の130件は、課税処理にコンピューターを導入した05年度以前に手続きが行われ、誤った課税を続けていた 住宅が建った際に建物の課税担当者が土地の担当者に連絡せず、土地への減税措置が適用されていなかったり、法務局から届く所有権移転登記の受理確認ミスで課税者が変更できていなかったり 取り壊した家屋の滅失届など各種届け出を所有者が市に提出し忘れ、家屋がなくなっているのに課税されていた 返還期限は地方税法上は過去5年だが、市側のミスが明らかな場合は「市返還金取り扱い要綱」に基づき20年前までさかのぼって返還 市内で課税対象となっている土地は26万1949筆、家屋は11万4145棟 16年度からは航空写真と課税台帳を照合できる新たなシステムを導入した。ただ、調査できるのは年間1万件ほどで、確認を終えていない課税者もかなりの数に上る |
| H29.2 | 茨城県 | つくば市 | 過去40年以上にわたって複数の納税者から固定資産税などを過大徴収 内の201の個人や法人から、過去20年で計1億2331万円を多く徴収 住宅の建つ土地の固定資産税を最大6分の1に軽減する特例を適用していなかったことなどが理由 同市は国家賠償法に基づき、過去20年に過大徴収した分に加算金の利子を加えて計1億6672万円を返還する方針 |
| H28.7 | 神奈川県 | 横浜市 | 軽減税率を適用する事務処理ミスで、約1300万円の課税誤り 市内の企業が機械装置など償却資産の一部について、市の条例に基づいて2008年度からの軽減税率適用を申請。しかし、本来12年度まで適用されるはずが、11年度までしか適用されず、約1300万円の差額が発生 担当職員がパソコンで適用期間の入力ミスをしたのが原因 |
| H27.10 | 兵庫県 | 宝塚市 | 都市計画で道路建設予定地となった市内の複数の土地について、1988年度から28年間にわたって固定資産税を過大に徴収していた 過徴収額は、資料が残っている96年度からの20年間で約3200万円に上り、28年間ではおよそ3700万円に上る 返還額は利息などを含めて計約4700万円になる見通し 過徴収されていたのは、市内の254件の土地 同市では、道路建設予定地になると新たに建築物を作ることへの制限がかかるため、固定資産税評価額を最大で3割減額する措置 担当者が都市計画のチェックを怠ったため、都市計画で決定された約8千件の予定地のうち254件が措置を適用されていませんでした 市議からの指摘でミスが判明 |
| H27.7 | 岡山県 | 岡山市 | 市内の男性から48年にわたって、過大に税金を徴収していた 1968年〜2015年度の約170万円分が過大に課税 岡山市内でアパートを経営している60代男性が所有する住宅用地について、課税額に影響する「敷地の間口」を実際より広く評価するなど、最大で年間約5万円を過大に徴収 岡山市はミスを認めたうえで、男性に約120万円を返還するとしている |
インターネット検索で1~2時間調べただけでも過去10年間でこの量です。これらは氷山の一角であり、公表されていないものも含めると、「潜在的過誤納者」は極めて多い可能性があります。
世間では、国が主体となって徴収する「所得税」「法人税」「消費税」や「社会保険料」「年金」ばかりに目が行きます。
しかし、ご自身が住まわれている自治体が課税する「固定資産税」等の賦課課税方式の徴収金が間違っていないか、またそれらの税金はどのような使途に使われているのか、どのように使うべきかの意識が上記ほど無いように筆者は思います。
地方税法では原則として過去5年分までの返還しか保証されていません(地方税法第18条の3)。
複数の自治体で10~20年分まで返還できるように取り決めた内部規定をおいているところもありますが、それ以上前になると基本的には返してもらえないことになるので、早めに調査を行うことが重要となります。
あなたやあなたの周りの方が支払い続けているその固定資産税は本当に「適正」なのでしょうか?

お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください